年代測定
(R5.18, R4.16, R2.18.27)
・炭素14法
:14C →14N,14C/12Cの割合を測定する
生物(死骸)に適用
・カリウム-アルゴン法
:40K→40Arの量を測定する
鉱物に適用
・アルゴン-アルゴン法
:40Arと中性子照射してできた39Arの比を求める
鉱物に適用
・ウラン-鉛法
:238U→206Pbと235U→207Pbの比を測定する
鉱物に適用
・フィッショントラック法
:238Uの自発核分裂による飛程の密度とウラン量から求める
鉱物に適用
オートラジオグラフィ
(R3.32, R1.25(物理))
イメージングプレート等を用いてRIの分布を可視化する
基本的な性能としてIP法>写真(フィルム)法
ミクロオートラジオグラフィでは低エネルギーγ線が適する
直接希釈法
(R5.25, R3.24, R2.26,R1.25)
目的物質が非放射性で,加える同位体が放射性である分析法
| 重量 | 比放射能 | 全放射能 | ||
| 添加前 | 目的の試料 | X | 0 | |
| トレーサ(RI) | a | S0=A/a | A | |
| 添加後 | 混合物 | X+a | S=A/w | S(X+a) |
*S(X+a) = S0×a
w:取り出した化合物の重量
逆希釈法
S0が既知で,目的物質が放射性で,加える同位体が非放射性である分析法
| 重量 | 比放射能 | 全放射能 | ||
| 添加前 | 目的の試料 | X | S0 | X×S0 |
| トレーサ | a | 0 | 0 | |
| 添加後 | 混合物 | X+a | S | S(X+a) |
*X×S0 = S(X+a)
二重希釈法
S0が未知で,目的物質が放射性で,加える同位体が非放射性である分析法
| 重量 | 比放射能 | 全放射能 | 重量 | 比放射能 | 全放射能 | ||
| 添加前 | 目的の試料 | X | S0 | X×S0 | X | S0 | X×S0 |
| トレーサ | a1 | 0 | 0 | a2 | 0 | 0 | |
| 添加後 | 混合物 | X+ a1 | S1 | S1 (X+ a1) | X+ a2 | S2 | S2 (X+ a2) |
*X×S0 = S1 (X+ a1)
= S2 (X+ a2)
アイソトープ誘導体法
直接希釈に適した同位体がない場合,
試料に結合する標識化合物で逆希釈法を行う
不足当量法
比放射能を求めるために行う
混合物の重量が必要ない
放射化学分析
(R2.32)
試料のRIの放射能,またはその娘核種の放射能によって存在量,存在核種を同定する方法
γ線スペクトルの測定を行う
その他の分析法への利用
(R4.32, R3.23 , R1.27(実務))
・ラザフォード散乱法
荷電粒子を試料に照射する
→散乱粒子のエネルギーを測定して元素を分析
・飛行時間(TOF)分析法
パルス状中性子を試料に照射する
→生成イオンの飛行時間を測定し,中性子のエネルギーを算出
そこから試料の質量を分析
・非破壊検査装置,γ線レベル計,硫黄分析計
γ線の透過(吸収)作用を利用
・厚さ計★
β線やγ線の吸収散乱を利用
・メスバウアー分光装置★
57Coの低エネルギーγ線(ドップラー効果)の共鳴吸収を利用
・中性子水分計
速中性子と水素の弾性衝突による熱中性子を利用
・蛍光X線分析装置★
光子の光電効果による特性X線を利用
・ECD
低エネルギーβ線の電離作用を利用
・煙感知器★
241Amのα線の電離電流の変化を利用
・静電除去装置
α線,β線の電離で生じたイオンを利用
・レベル計★
高エネルギーγ線放出核種
・陽電子消滅法★
:22Naのような長半減期を用いた物質の性質を調べる方法
・即発ガンマ線分析★
:高エネルギーガンマ線を用いた中性子放射化分析の一種
直接飽和分析法(Direct-saturation-analysis-DSA)
・T3摂取率測定法
・不飽和鉄結合能測定法(UIBC)
競合的ラジオアッセイ(Competitive-radioassay)
・競合的蛋白接合(能)測定(CPBA)
・放射免疫測定法(Radioimmunoassay-RIA)
:既知量の非標識抗原と,一定量の標識抗原と,一定量の抗体を競合反応させた後にBF分離してBの放射能を測定して標準曲線を製作する
同様にして未知量の試料検体の抗原のBの放射能を測定して,標準曲線から試料中の抗原量を求める
特異的結合蛋白(抗体)と標識抗原の量は一定
・放射受容体測定法(Radioreceptor assay-RRA)
非競合的ラジオアッセイ(Non-competitive radioassay)
①免疫放射定量測定法(Immunoradiometric assay-IRMA)
→ 使用できるならRIAより優れた検査方法
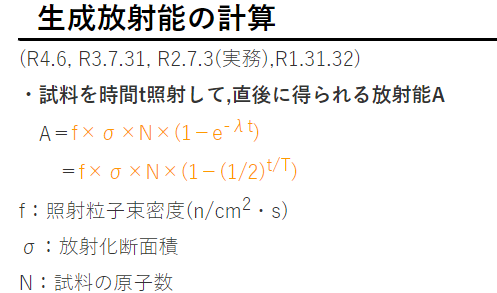
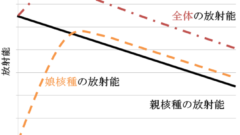
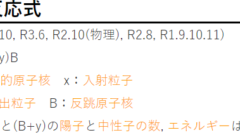
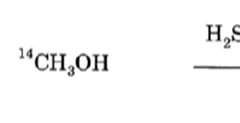
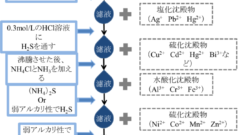
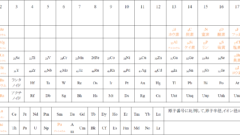
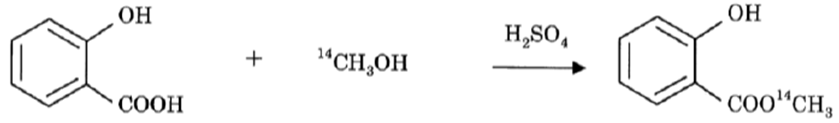
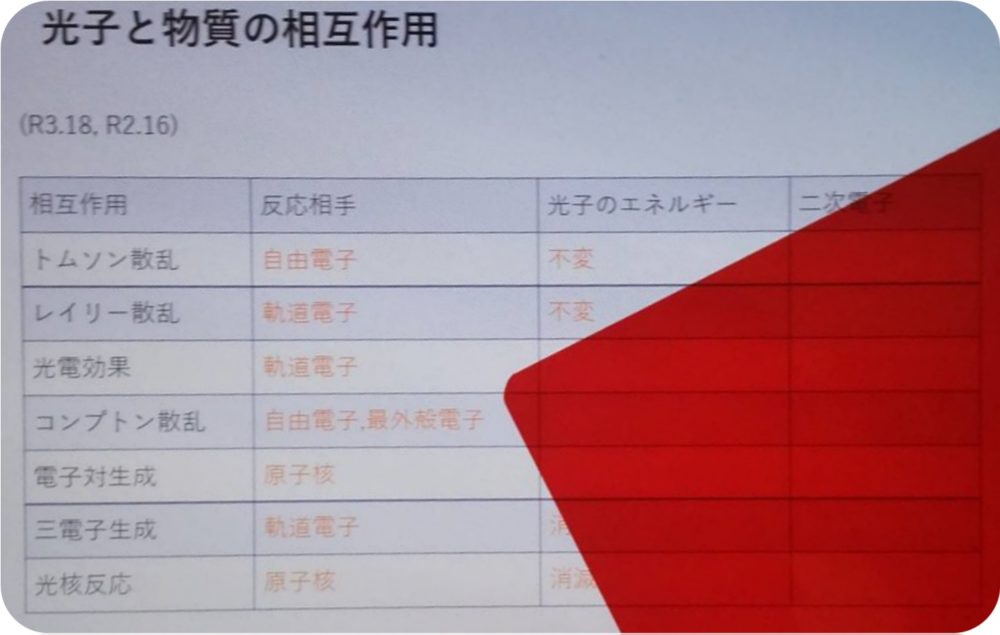


コメント