DNA
(R5.32, R4.11, R3.31, R2.31)
・デオキシリボ核酸(DNA)の構造
DNA=ポリヌクレオチド(ヌクレオチド)
=(塩基+糖(デオキシリボース)+リン酸)×2本
塩基:A –(2本の水素結合)- T,G –(3本の水素結合)-C
A(アデニン),G(グアニン)はプリン塩基
T(チミン),C(シトシン)はピリミジン塩基
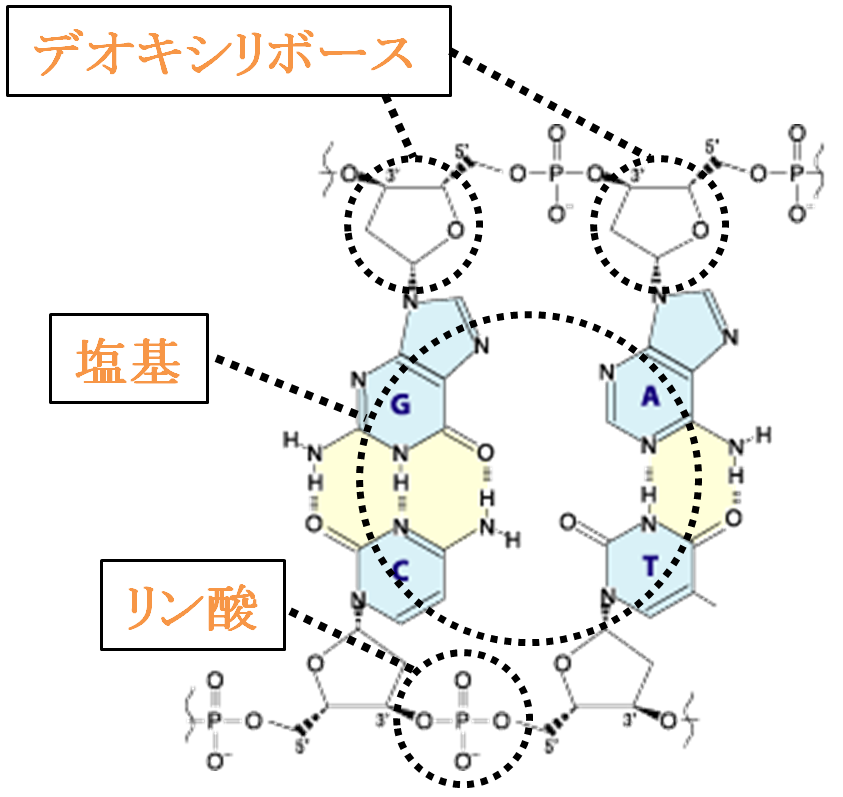
・DNA複製材料
:dATP,dTTP,dGTP,dCTP
・DNAの損傷(R2.16,R1.14)
起きやすい順番≒細胞死への影響が少ない
:塩基損傷>塩基遊離>1本鎖切断>2本鎖切断
その他に架橋形成がある
塩基損傷はOH*によって起こりやすい
塩基遊離はプリン塩基に起こりやすい
*放射線特有の損傷というものはない
*ピリミジンダイマ
:隣接する塩基の共有結合(紫外線による),T – Tに起こりやすい
クロマチン
8つのヒストンタンパク質の周りにDNAがおよそ2回巻きついた糸巻きのような形の「ヌクレオソーム」が数珠状に多数連なった構造
DNAの修復
(R5.32, R4.31, R2.31,R1.15)
・DNAの損傷
1Gy(γ線)照射で1本鎖切断は約1000個,2本鎖切断は約40個
・一本鎖の損傷
:大部分が数分以内に修復される
(1)光回復
:損傷の直接消去
(2)除去修復(R5.14)
:塩基,ヌクレオチド,ミスマッチの除去
APエンドヌクレアーゼ:DNA塩基除去修復経路(BER)に関与する
(3)組み換え修復
・二本鎖の損傷
(R5.32, R4.14, R3.18, R2.32,R1.32)
:修復には数時間かかり,突然変異や細胞死に繋がりやすい
(4)非相同末端結合
全細胞周期で起こりうる
切断端の損傷部位が取り除かれた後,直接ヌクレオチドが挿入されて再結合が起こる
間違った遺伝情報を持つようになる場合が多く,染色体の組換えなども起こしやすいので,細胞の機能を回復できない場合がある
DNA結合触媒サブユニット:DNA-PKcs,
DNA依存性プロテインキナーゼ:DNA-PK(Ku70,Ku80),XRCC4
などのたんぱく質の働きによる
(5)相同組み換え修復
(R2.19)
姉妹染色分体の存在する S期の終わりからG2期に起こりうる
ヌクレアーゼとヘリカーゼによって一本鎖部分が残るように切断端の前後が切出され,損傷を受けていない 相同な染色体DNAとの交叉が起こって正常染色体の遺伝情報を用いてDNA合成がなされ,最後に交差部分が切断・再結合されて修復を終える
間違った修復を起こさず,完全に回復する
*色素性乾皮症
:紫外線に高感度で,ヌクレオチド除去修復ができない
*DNAリガーゼ (R3.31)
:3′-水酸基と5′-リン酸基の間をリン酸ジエステル結合でつなぐ役割
突然変異
(R5.18, R4.14, R3.22.23, R2.19.20)
放射線の染色異常:構造異常(数の異常はおこらない)
線量率効果がある
・染色体異常の型
1,安全型
:欠失(部分的消失, 発生が多い),
逆位(二か所の切断で逆向きに融合する),
転座(一部が移動)
などがある
細胞分裂可能であり,長期生存し,発がん等の原因になる
2,不安定型
:環状染色体,2道原体染色体(G1,G2期の被ばく)
細胞分裂が難しく,早期に細胞死する
・染色体型異常
:染色分体の同じ場所に二か所切断がある
G1期に起こる
・染色分体型異常
:染色分体の一方に切断がある
G2期に起こる
*姉妹染色分体
:S期に合成された同じ遺伝情報を持つ染色分体同士で,交換があっても遺伝異常は起こらない
・被ばく線量の推定
末梢リンパ球を培養し,染色体異常の頻度を観察する
観察対象は環状染色体や2道原体染色体が多い
コドン
(R5.32, R4.31, R3.31, R2.31,R1.31)
遺伝暗号の単位
核酸(mRNA)を構成している3つの塩基配列で,4種の塩基(アデニン,グアニン,シトシン,ウラシル)によって構成される
64通りの組合せがあり,そのうち3つが終止コドンとなっている
*3塩基で1セットなので,(3n+1)番目がコドンの始まりとなる
・ミスセンス変異
:塩基の置き換わりによるアミノ酸の変化によっておこる変異
鎌状赤血球貧血
・ナンセンス変異
:塩基の置き換わりで終止コドンになってしまい,翻訳が停止する変異
・フレームシフト
:塩基欠損または塩基挿入によって,塩基ずれが起こり,その後ろのアミノ酸指定がずれる変異

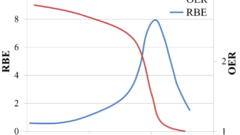
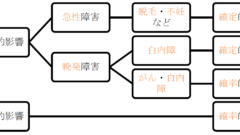
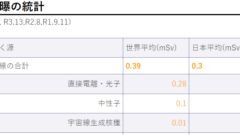
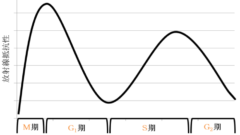
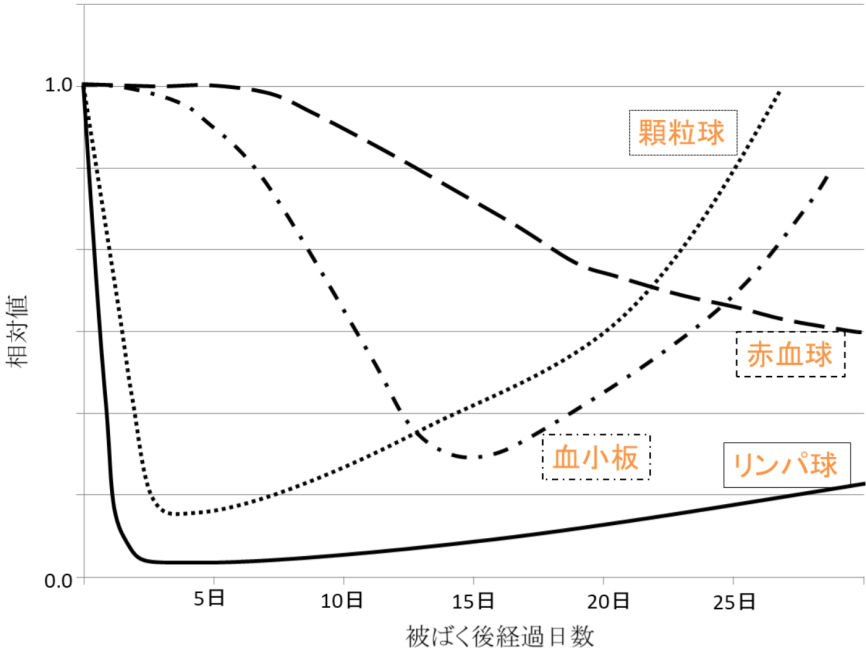
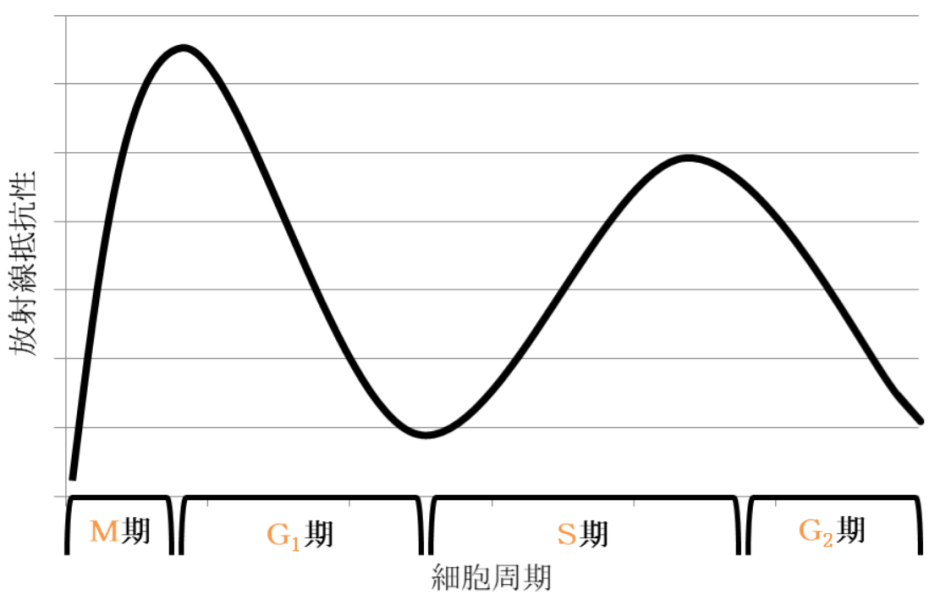
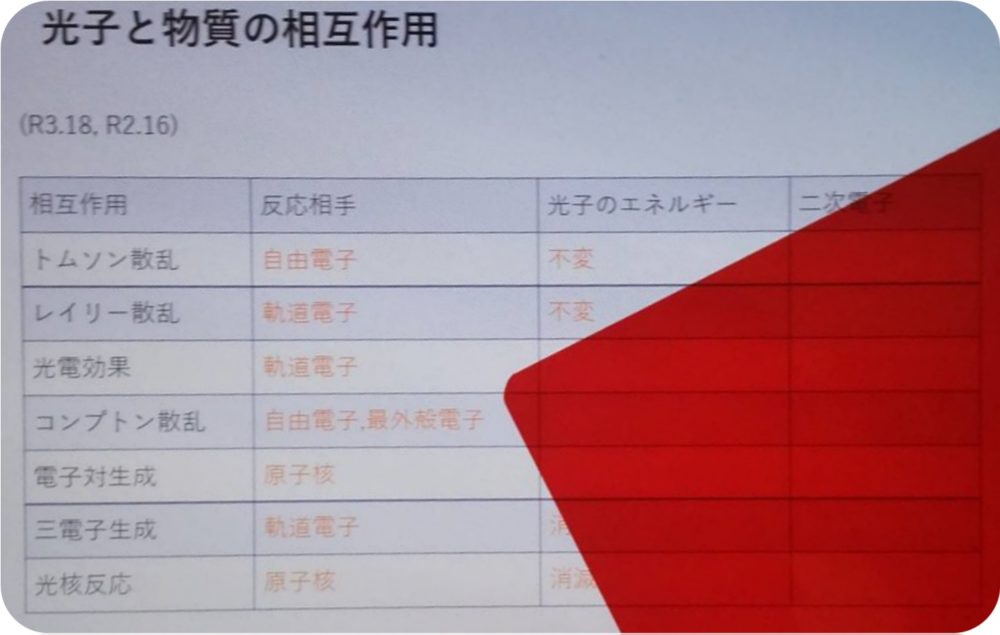


コメント